
浜松RB通信
発行:1999.10.01. 浜松RB広報班編集部
浜松市総合防災訓練に14名が参加
入野中学校をメーン会場に、周辺地区で訓練を展開

9月1日、浜松市総合防災訓練が入野地区で開催されました。平日にもかかわらず「浜松RB」から14名の隊員が参加しました。
午前8:30、主会場となった入野中学校に隊員が集結、笠原隊員のバスを「浜松RB移動本部」として設置、サポート隊員が配置につきました。
佐野バイク隊長が、訓練本部に出動隊員数を報告、訓練本部からは、入野地区の「崖くずれ等の被災状況の調査」及び、「被災地報道班からの撮影ビデオの回収」を任務として与えられました。直ちにバイクを二班に分けて被災地に出動。
シナリオのない訓練
今回の総合訓練は、より実践的な防災訓練をめざした「シナリオのない訓練」となりました。訓練本部から出される指令のもとに活動するとともに、各参加団体が自らの参加目的のもとに、自発的な活動を行いました。
災害時には欠かせない「RB肩章」
「浜松RB」が指令を受けた活動の一つが「被災地報道班から撮影澄みビデオを回収し訓練本部に届ける」ことでした。ところが、出動先には多くのマスコミ関係者がおり「誰」が報道班なのかわからず任務を果たすことができませんでした。
災害時には、お互いに自分(達)が「何者」であるか身分を明確にすることが重要であることがわかりました。浜松RBでは、今回初めて「RB肩章」をつけて参加しましたが、隊員同士は勿論、第三者からも識別しやすく大変好評でした。
今回の訓練により、「RB肩章」は災害時において「RB隊員」が訓練された災害救援隊であることを証明するうえでなくてはならない装備品となりました。勿論、日頃から警察や行政、市民との信頼関係を深めていくことが大切ですが…。


全員が「RB肩章」を装着 班ごとの打ち合わせ





FM放送局へ情報を伝達
自発的な訓練として、今回はじめてFM放送局への情報伝達訓練を行いました。バイク2台が1チームとなって、被害状況を記録した「被災地情報カード」を「FM静岡」「FMハロー」に届けました。両局とは日頃から連携を取り合っていますが、この日は事前連絡なしで実施しました。「FMハロー」では、情報を届けた五明隊員が急遽、生番組に出演。「浜松RB」が届けた情報は30分後に放送されました。これにより、「RB」と「放送局」の連携プレーの威力が実証されました。

各参加団体が本部前に整列。市長はじめ訓練本部からの講評を聞いて解散。
浜松RBから10名が参加
「浜松RB移動本部バス」が出動
第3回JRB全国大会には「浜松RB」から10名が参加。今回は、奈良県に大震災が発生したという想定のもとに全国のRBが救援に駆けつける「集結訓練」を兼ねて開催された。「浜松RB」では施設班の笠原班長所有のバスを「浜松RB移動本部」に仕立て、オフロードバイク1台を積載して前日の3日に浜松を出発。東名・名神と進み、被災地に近づいて進入が困難となった所に移動本部を設置、そこから先は偵察バイクを出して被災地の情報を収集して「浜松RB」に連絡、後続の支援バイクを待つという想定のもとに訓練を行った。しかし、同乗予定の3隊員が仕事の都合でドタキャン。笠原班長と内田代表の2名になってしまったため、一部、シミュレーションのみとなった。バスには8名が乗れるが、この経験から本部機能を果たすには最低4名が必要ということがわかった。
 竹内・内藤潤隊員
竹内・内藤潤隊員  鈴木隊員
鈴木隊員
浜松から奈良までの約300kmをオフロードでかけつけた鈴木・五明・竹内・内藤の4隊員の第一声は「ケツが痛〜い」だった。
でも、その痛さは今大会主催者の[JRB近畿ブロック]の仲間に確実に伝わった。
この日も迷彩服で身を固めた鈴木隊員は、周囲から自衛隊員と間違われたが、「浜松から奈良を助けに来てくれた」という強烈な印象を残した。また、深夜にかけての交流も大きな成果。皆さん本当にご苦労様!
でも世の中には上を行く者がいた。バイクのプレートを見れば、東京や神奈川、広島もある。大分県と鹿児島県からフェリーを乗り継いで駆けつけたバイク隊員もいた。大分県は女性の隊員だった。いずれも脱帽、あっぱれ!
トランスポートで参加
長内・森江・伊堂の3隊員は、さすがに中年らしく体力を考えた方法で参加した。
彼らは、常日頃から長距離ツーリングの際には、長内隊員所有のトランスポートにオフロードバイクを積み込んで途中の退屈な距離を荒稼ぎし、一番おいしいコースをバイクで走破するという贅沢な余暇を楽しんでいる。車内には、ベッドスペースもあるからホテルは不要。今回も、深夜に会場に到着し、朝まで睡眠という健康コース。だから、元気ハツラツ。目が醒めればすぐRB活動が開始できる実戦向き。震災は厳冬期かも知れないし、今回のように途中で大雨に会うかも知れない。その時、トランスポートが役立つことを彼らが実証してくれた。
全国から100台のバイクが集結
全国から100台のバイクが集結


集結訓練終了後は、「なら100年会館」に会場を移して記念式典が行われた。行政、消防関係の来賓祝辞のあと、各RB代表が登壇し、震災時相互支援協定書に調印、いざという時の協力を誓い合った。
その後、阪神・淡路大震災のドキュメント映画を鑑賞して式典を終了。
その後、宿泊地の「奈良市青少年野外活動センター」に移動。JRB近畿ブロックの皆さんの料理による夕食、そして、キャンプファイヤー、さらに、各部屋での交流が
記念式典では各RBが相互支援協定を締結 夜明け近くまで続いた。

JRB常任理事会で定款を可決。認証手続きを東京RBに付託
これまでの経緯
これまでの「JRB」は、全国の各RBで構成されていたが、あくまで任意のボランティア集団で、その運営を支えるための経費や人的負担も、その義務もなかった。これまでは「浜松RB」が何とかその代行を果たしてきたが、全国的な展開とともに自立できる全国組織としての確立が必要になってきた。そこで、3月に開催された常任理事会において、NPO法によるJRBの法人化が決定され、それに伴う定款案の作成が「東京RB」に付託されていた。そして、今回の常任理事会において、その定款案を審議することになっていた。
深夜の常任理事会で定款を承認
常任理事会は、キャンプファイヤーもビールも抜きで、午後7時から始まった。浜松RBからは、内田代表、内藤副代表、柴田隊員(監査)の3名が出席。内藤・柴田隊員は仕事の都合で、それぞれ別の車で奈良入りし翌朝には帰浜した。
常任理事会では定款の審議が最大のテーマとなった。議案は1ヶ月前に各常任理事に配布され、問題点を検討してくることになっていたので、直ちに審議に入った。10章から成る定款は章ごとに審議され、出席者全員が意見を述べ、オブザーバーも参加して熱心な議論が交わされた。問題は一つ一つ解決され、最後は全員賛成のもとで「特定非営利法人JRB定款」は承認された。また、認証先の監督官庁が経済企画庁になるため、認証の手続き一切が「東京RB」に付託された。すべての審議が終了したのは何と、深夜午前1時半だった。実に6時間半に渡る審議となった。今後、順調に手続きが進めば、来春にはJRBの法人化が実現することになる。
法人化が実現すると
法人化が認証されると、これまでの規約に基づくJRBは解散し、定款に基づいた社員によって新生「JRB」が誕生することになる。ここでいう「社員」とは、個人会員ではなく定款に賛同して参加した団体会員(都道府県RB)をいう。社員は、総会における発言権を有すると同時に、JRBの運営上の責任と義務を有することになる。そして、社員となったRBの隊員すべてがJRBの会員となる。
第1回の総会は東京で開催
今後は、総会がJRBの最高決議機関となる。総会は毎年1回開催され、第1回総会は東京で開催されることになった。また、これまでの全国大会は、各ブロックごとの災害時相互支援システムを実現していくうえで重要なことから継続となり、来年は中国ブロックの「島根RB」の主幹で開催することが決まった。
静岡県内ネットワークの充実
法人化に伴い、団体会員の単位が「都道府県RB」となったことから、浜松・清水・静岡・沼津の4つのRBを持つ静岡県として、県内RBの一体化が必要になってきた。そこで、各RBが支部としてお互いに独立しながらも、いざという時には、各RBが相互に連携して支援活動ができるような組織にするため、「沼津RB」が幹事役となって「静岡RB」設立について研究することになった。
上級救命講習会 参加者募集!
下記の日程で上級救命講習会を開催します。災害時には応急手当が必要な場面に出会うことや、隊員自らが負傷することも予測されます。その時、役立つのが心肺蘇生や応急止血などの救急救命法です。これは、災害時のみならず、日常においても役立ちます。特に心肺停止の場合には、救急車が駆けつけるまでの5分以内の処置が生死を左右するといわれています。もし家族がそうなった時、あなたならどうしますか!備えあれば憂いなしです。「浜松RB」では、全隊員の受講をめざし、年に2回の講習会を開催しています。1度受講しただけでは忘れてしまいますので、身につくまでは1年に1回以上の受講をおすすめします。同封の申込書に記入のうえ,FAXまたは郵便にてお申し込み下さい。
開催日:平成11年11月14日(日)午前8:00〜午後4:30(集合7:45)
会 場:浜松市消防本部6Fホール
申込み:TEL/FAX 053-425-4769(担当:佐藤正浩まで)
浜松RB忘年会 参加者募集!
好評の忘年会がやってきました。何故か、普段、見かけない仲間が集まるのが、この会の特色。「総会や訓練は大半が昼間なので、なかなか参加できない」という方、是非、ご参加ください。「飲んで語る・歌う」ことからお互いの交流が深まり、いざという時の助け合いにつながります。そうです。ここでは、全員が同じ目的を持った仲間ばかり。自発的に参加することがボランティアの原点。初めての方も、久しぶりの方もここに来れば、全員が仲間。恋人だって見つかるかも!
開催日:平成11年12月11日(土)午後7:00〜
会 場:グランドホテル浜松 タイムズスクエア(浜松市東伊場1-3-1地下1階)
会 費:男性¥4.000円/女性¥3.000円
■会計からのお願〜い!
皆さん、会費の納付はもうお済みですか?今年度より「浜松RB」は、会費に
よって運営されるようになりました。この機関紙も会費で発行されています。
■ 会費の額:年額¥2.000円
■ 納付方法:以下の納付方法の中から都合のよい方法を選んでください。
1)静銀からの振込(振込手数料は、別途お支払い下さい)
振込先:静岡銀行浜松支店 普通口座 0994491 浜松RB 金子鉄男
2)ライダーズルーム・オオゼキに納付。
3)浜松RB定例会、またはRB研究会に出席した時に納付。
■納 期:期限はありませんが、その年度分を前納するのが基本です。できる
だけ早い納付をお願いいたします。
■ 注意事項:振込以外の場合は、トラブル防止のため必ず領収証と引き換えに
お支払い下さい。控えは事務局で保管し会員名簿の資料となります。
「浜松RB有玉事務所」を開設
11月から「定例会」の会場に!

 事務所内部
事務所内部 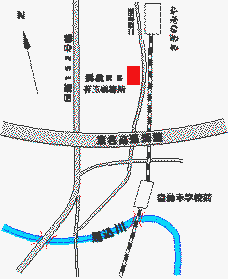 有玉事務所付近案内図
有玉事務所付近案内図 9月1日より「浜松RB有玉事務所」が開設されました。これは、施設班の笠原班長が会社の一室を浜松RBの有玉事務所として提供してくれたものです。
これにより、11月からの「浜松RB」の定例会は同事務所で開催することになりました。場所は、遠鉄西鹿島線と並行している「二俣街道沿い」で、同鉄道の「さぎの宮駅」と「遠鉄自動車学校前駅」の中間点にあたります。事務所は道路添い(西側)で、2階建て建物の1階にあります。窓には「浜松RB」の看板が掲げられています。道路の東側には遠鉄西鹿島線が走っていますので、とてもわかりやすい場所です。
「定例会」は、浜松RBの事業を推進する場所です。訓練やツーリング、総会や忘年会の計画の立案・準備等、隊員の自発的な参加によって運営されています。「RB通信」発行時には、手分けして「折り」「封筒詰め」の作業も行っています。今後は、各班の会議や打ち合わせにも利用していく計画です。隊員の皆さん、是非、場所を覚えて下さい。そして、「定例会」にも是非、ご参加下さい。
駐車場もあります。が…!
事務所の向い側に駐車場がありますが、台数に限りがあります(7〜8台)。乗り合わせのできる方は、一緒にお出かけ下さい。
所在地:〒431-3122浜松市有玉南町90(笠原配管内) 電 話:053-434-1401(笠原配管) 携 帯:090-1231-4348(笠原義雄)

RB本部:浜松市西塚町325-1(ライダーズルーム・オオゼキ内) TEL/FAX:053-463-1033
事 務 局:浜松市東若林町1220-5 TEL053-448-7119
有玉事務所:浜松市有玉南町90 TEL053-434-1401
インターネット事務局:E-mail te-taro@wa2.so-net.ne.jp